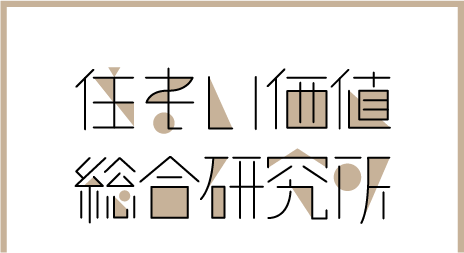創樹社が主宰する住まい価値総合研究所(スマカチ)は、2025年1月22日に第97回スマカチ・シンポジオ「建設DXによる課題解決の可能性」を開催した。
今回は、DX化によって建設業界における労働環境のデジタル化を図り、作業効率・生産性の向上を目指す「建設DX研究所」の岡本杏莉代表((株)アンドパッド 上級執行役員 経営戦略本部長)を講師に迎え、建設DXにおける最新の政策動向などを聞いた。
急務となる建設DX化
近年、まちづくりや再開発事業が活発化し、建設需要が高まっている。
一方、建設業界では人手不足が常態化。2024年4月からスタートした時間外労働の上限規制をはじめ、昨今の法改正がこれに拍車をかけており、業務負担が増大している。加えて、25年4月には改正建築基準法、改正建築物省エネ法の施行も控えており、業務負担はさらに増えることが予想される。
そこで重要となるのが業務のDX化だ。現場技術者の作業をみると、全体の6割を行政手続きや施工データの整理、書類作成、資材の受発注といった事務的作業が占める。なかでも行政手続きについては、自治体ごとに書類の様式や提出ルールが異なるほか、電子化が進んでいないことなどから負担に感じる建設事業者が多い。同研究所が行ったアンケートによると、住宅事業者は55.6%、ゼネコンは68.7%が行政手続きに負担を感じると回答している。
岡本氏は、建設DXが進むことで、こうした事務手続きの効率がアップし、業務負担の軽減につながると指摘する。

なお、同研究所では建設DXの推進活動として、関係省庁などに向けた政策提言を実施。先に述べた行政手続きの課題についても継続的な提言を行っているところだ。
また、岡本氏はDX化による実際の効果事例として、同研究所の事務局を務めるアンドパッドが提供するサービス「ANDPAD」の導入事例を紹介した。
ANDPADは、施工スケジュール管理や現場写真の整理、書類作成、電子受発注などの機能を備えたクラウド型の建設プロジェクト管理サービス。このうち電子受発注を使用した事例では、これまで発注業務にかかっていた時間を8~9割削減できたという。
DX化に向けた法改正が進む
建設DXに向けた法改正も進んでいる。22年12月に、デジタル庁があらゆる業種におけるアナログルールを見直すプランを策定。建設業については、①監理技術者等の兼任要件の緩和、②特定元方事業者による巡視の遠隔化の二つが図られているところだ。
①では、これまで請負金額4000万円以上の工事については、各現場に専任の監理技術者を配置しなければならなかったところ、一定のICT活用などの要件を満たす場合には、監理技術者を2現場まで兼任で配置可能とする法改正が24年12月に施行された。
また、②では現場の安全水準が低下することがないように留意した上で、定点カメラやモバイルカメラを活用した現場の遠隔巡視の許諾が厚生労働省から通知されている。一方で、週に1回は目視による現場の巡視が適当であるなどの留意事項も示している。
ただ、小規模な現場における人手不足の深刻さなどを踏まえると、実態に合わない部分も多分にあることから、「安全確保が可能なことを前提に、今後のさらなる緩和が期待される」と岡本氏は締めくくった。