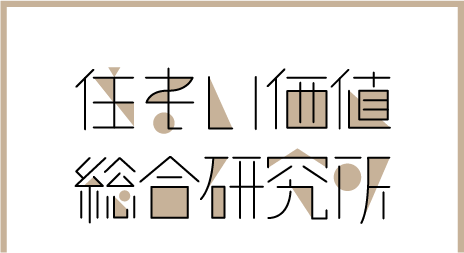創樹社が主宰する住まい価値総合研究所(スマカチ)は、2025年4月18日に第99回スマカチ・シンポジオ「これからの住宅業界の行方」を開催した。今回は、国内外の住宅金融市場などに詳しいニッセイ基礎研究所の小林正宏氏を講師に招き、この先の住宅マーケットを予測してもらった。

縮小する住宅規模
社会変化に合わせた商品転換を
日本の住宅市場は、急激な人口減少と世帯構造の変化に伴い、かつての「大量供給・大量消費」から「縮小と質的変容」のフェーズへと明確に移り変わっている。2024年の日本人人口は前年から86万人余りも減少した。こうした社会変化は住宅市場において「空き家問題」や「住宅の小規模化」として顕著に表れている。
現状、空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%に達しており、特に中国・四国地方などで多い。また、新築着工戸数は長期的な減少トレンドが続いており、現在は年間80万戸前後で推移している。一部の有識者からは、「(人口減少社会を踏まえると)80万戸でも多いのではないか」という意見も聞かれる。
供給される住宅の実態にも大きな変化がみられる。その一つが、1戸当たりの床面積の縮小だ。特に注文住宅については、ピーク時の1996年に平均140.8㎡だったものが、2024年には平均113.3㎡まで縮小している。30年経たずに27㎡も床面積が小さくなっている。
この背景には、従来の「標準世帯(4人家族)」が今や全体の2割にも満たず、単身・2人世帯が全体の6割を占めるという世帯構成の変化がある。もはや、かつてのように大規模な住宅を求める需要層は少数派になった。
また、住宅ローン市場に目を向けると、日米の対照的な構造が浮き彫りになる。アメリカでは全期間固定金利の利用者が約9割を占めるのに対し、日本では変動金利型が7割超という圧倒的なシェアを占めている。加えて、近年では物件価格の上昇に対し、毎月の返済額を抑えるために返済期間を40年や50年に延ばす動きも活発化しており、こうした金利商品を取り扱う金融機関が増えている。
さらに、マンション市場については、首都圏における2024年度の平均価格が8135万円と高騰を続けている。これを支えているのは、世帯年収1000万円を超えるパワーカップルなどの実需層だ。例えば東京都特別区部では、子育て世帯の56.2%が世帯年収1000万円以上であり、こうした人々が1億円前後の物件を支えている。
課題は資産価値の維持管理
今後、国内住宅市場で最大の課題となるのは、住宅の「資産価値の維持」である。アメリカでは住宅投資額以上にストックの時価総額が積み上がっているのに対し、日本では過去30年間に780兆円もの住宅投資をしながら、建物の価値の大半が消滅し、現在の建物時価総額は471兆円にとどまっている。
家を「使い捨ての消費財」から「価値が維持される資産」へと変えるためには、適切なメンテナンスを通じた価値維持の意識変革が不可欠だ。小林氏は、「住宅を負の遺産にしてしまうのではなく、真の資産として機能させていくことが重要である」と結んだ。