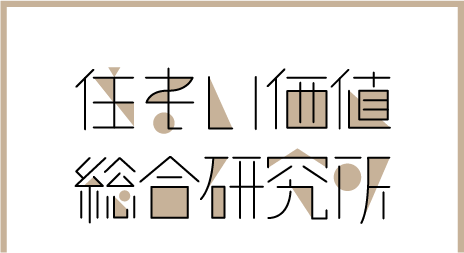創樹社が主宰する住まい価値総合研究所(スマカチ)は2024年10月21日に第95回スマカチ・シンポジオ「今、企業に求められるカスタマーハラスメント対策」を開催した。
パーソル総合研究所が実施した「カスタマ ーハラスメントに関する定量調査」によると、顧客折衝があるサービス職の35.5%が過去に顧客からのハラスメント・嫌がらせを受けた経験があり、ここ3年で職場でのカスハラが増加したという回答も32.6%に達している。
果たして、住宅業界はどのようなカスハラ対策を講じていくべきなのか―。
パーソル総合研究所の上席主任研究員である小林祐児氏と、研究員の田村元樹氏を講師に迎えて、前出の調査の結果などを踏まえながら、企業のカスハラ対策について解説してもらった。
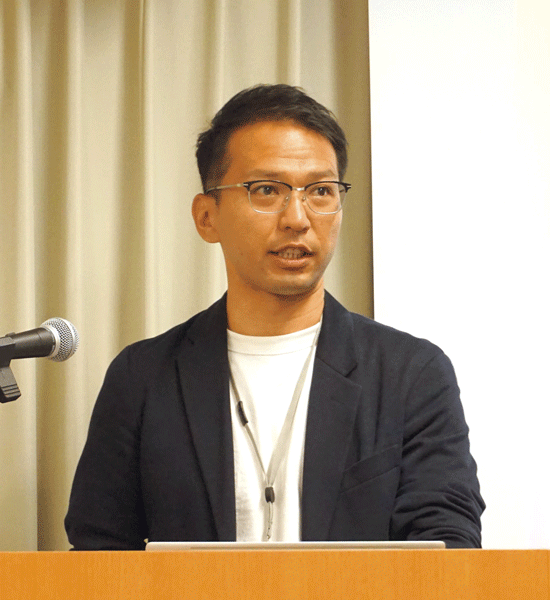
カスハラがサービス職の 人材不足を加速
田村氏からは、カスハラに関する国や自治体の動向、さらには実態などについての話があった。パーソル総合研究所のアンケート調査によると、顧客との折衝があるサービス職のうち、35.5%がカスハラを受けた経験があると回答しており、その被害内容は「暴言や脅迫的な発言」が6割以上を占めている。
カスハラの加害者については、女性よりも男性が多く、年代別では高齢層ほど多くなる傾向にあり、中でも高学歴で社会的地位が高い職業に就いていた高齢者が加害者になる傾向が強いという。
また、カスハラを受けた直後、4割弱が「仕事を辞めたい」と考え、カスハラの経験がある層の転職意向が1.8~1.9倍高いという調査結果もある。こうした状況下で、「多くの職場でカスハラが『我慢され』、『放置され』、『無視され』ており、サービス職の人材不足を加速させている」と田村氏は指摘する。
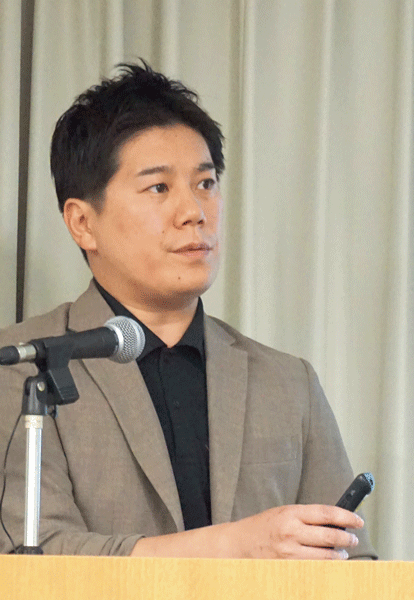
「防ぐ」、「教える」、「強くする」が企業対策の基本
小林氏の講演では、企業のカスハラ対策について基本的な考え方などを解説。小林氏は、企業側のカスハラ対策として、「防ぐ」、「教える」、「強くする」が重要であると指摘する。
「防ぐ」は、カスハラを未然に防ぐ対策。例えば、あるコーヒーショップでは、レシートやネームプレートにスタッフの名前を記載しない方針へと切り替えたという。また、最近ではAIが電話対応なども行うシステムも開発されており、こうしたツールも活用し、カスハラ発生を防止することが求められている。
「教える」では、カスハラ対応マニュアル、被害者へのケア・保護方針などを作成し、社内での対応を適正化していくことが大切になる。同時に、研修などを通じてカスハラへの対応力を強化していくことも求められる。小林氏は、「まだ具体的な対策を講じていない企業の場合、まずはカスハラ事例のレポートの蓄積や分析、共有からはじめるのがいいのではないか」としている。
最後に、「強くする」という点では、「信頼資産」が高く、「心の負債」が低い組織づくりが肝要になるという。そのためには内部コミュニケーションを活性化し、現場長のマネジメント能力の向上を図っていく必要がある。
顧客折衝が多い住宅業界でも問題になってきているカスハラ。まずは企業として「防ぐ」、「教える」、「強くする」ための取り組みを進めていくことが重要になりそうだ。