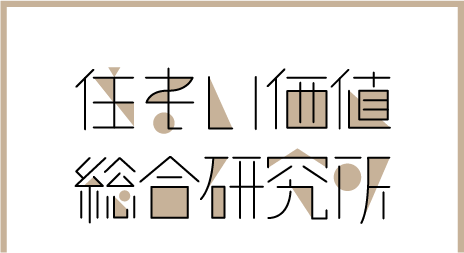創樹社が主宰する住まい価値総合研究所(スマカチ)は 2024年11月20日に第96回スマカチ・シンポジオ「減らない子どもの家庭内事故~住宅業界が本気で取り組むべきこととは~」(スマカチ研究会『住宅と子育ての関係を考える』第3回)を開催した。長年にわたり子どもの事故予防に取り組んできたNPO法人Safe Kids Japanの理事長で小児科医の山中龍宏氏を講師に迎え、家庭内での子どもの事故の実態などを聞いた。
子どもに多い「コピペ事故」
東京消防庁のデータによると、日常生活における子どもの緊急搬送件数の第1位が「転落」となっている。特に、2014年から2021年の0歳~2歳の搬送件数の推移を見てもその傾向はほぼ変わらず、「どこから転落したか」では、0歳はベッド、1・2歳は階段が毎年1位。子どもの事故はコピペのように同じことが起きていることから、「コピペ事故」とも呼ばれている。
欧米では2000年頃から子どもの事故に対する考え方が変わり、予測できない避けられない事象という意味の「アクシデント」(事故)から、「インジャリー」(傷害)という言葉が用いられるようになっている。子どもの転落や誤飲などは予測できる、という考えに基づくものだが、さまざまな統計データを見る限り、子どもの事故件数は減っておらず、「予防活動が機能していない状況」(山中氏)だという。

高所からの子どもの転落を防ぐために
子どもが住宅の窓やベランダから転落する事故が後を絶たない。東京都製品等安全対策協議会によると、ベランダからの転落で緊急搬送された12歳以下の子どもの事例は平成19年以降で145件発生。2歳児が最も多いが10歳以上でも起きている。Safe Kids Japanは2017年に10歳以下の子どもを持つ家庭を対象に、オンラインアンケートでベランダの使用状況を調査した。ベランダからの転落事故についてはほとんどの人が知っていたが、「対策をしている」との回答はわずか3割だったという。回答者から投稿された写真を見ると、足を掛けやすいベランダの柵の形状や室外機の置かれ方などから、転落のリスクがある事例も散見された。こうした現状を踏まえ、同法人では調査結果をもとに高所からの転落を防ぐための啓発用パンフレットを作成・配布するほか、自治体と連携し、子どものいる家庭に出向いて窓に補助錠を設置する活動も進めている。
また、6階建てマンションのベランダから4歳の子どもが転落死したことを踏まえ、ベランダの柵の高さを120cm、130cm、140cmの3種類設定して事故原因を検証した結果、ベランダの柵を上げることは3、 4歳児まではある程度の効果がみられたものの、140cmまで高くしても5歳児ではほぼ効果がみられなかったという。このことから山中氏は「建築基準法を警察の情報なども取り入れて見直す必要があるのではないか」と指摘した。
さらに、「住宅での事故予防のためには細かい現場検証が重要になる。子どもに限らず、すべての事故を防ぐことはできないが、医療機関を受診しなければならないような重症度が高いケガについて詳細な情報を得て取り組まなければ具体的な予防にはつながらない。住宅関係の方々が事故予防について何らかの形で継続的に取り組んで欲しい」(山中氏)と訴えた。