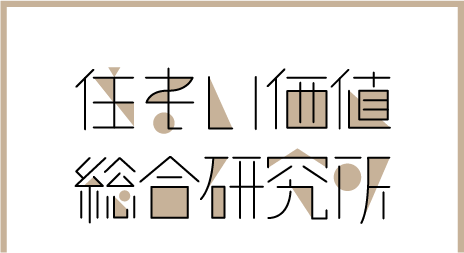創樹社が主宰する住まい価値総合研究所(スマカチ)は、 2025年5月16日に第100回スマカチ・シンポジオ「作り手不足の克服へ 新たな住宅生産方式は誕生するのか!?」を開催した。
今回は、東京大学大学院・准教授の権藤智之氏を講師に迎え、日本におけるプレハブ住宅の歴史や海外の動向、今後の住宅設計の在り方などについて話を聞いた。
プレハブ住宅の発展と海外の建築動向
戦後、日本では深刻な住宅不足が発生。これを解消しようと、建築家の前川國男が1946年に木質パネルを使ったプレハブ住宅「プレモス」を提案したが、あまり普及しなかった。その後、不燃化の観点から誕生したのがプレキャストコンクリートを使った「プレコン」。積水ハウスや大和ハウスなどが商品開発に着手し、プレハブ住宅は木造からコンクリート造に切り替わっていった。
そして、60年代には軽量鉄骨を用いた大和ハウスの「ミゼットハウス」や積水ハウスの「セキスイハウスA型」、松下電工の「松下1号型住宅」などが登場し、プレハブ住宅は低価格・高品質・短工期の利点を活かして市場を拡大していった。こうした結果、70年代頃には住宅不足問題は解消。やがて、住宅メーカー各社の商品開発は、差別化を図るべく消費者ニーズに応えるものへと移行していった。
一方、海外の様子をみると、スウェーデンなどでは木質化と工業化が結び付いた木質モジュラー住宅が発展しており、年間2000個のユニットを供給している工場もある。また、シンガポールではDFMA(Design for Manufacturing and Assembly)が国を挙げて推進されている。これは、製品の設計を簡素化し、製造のしやすさと組立効率の向上を図る手法で、簡単に言えば工場生産を徹底するということ。さらに、アメリカではオフサイト建設が職人不足の解決策として注目され、木造プレハブ住宅の開発が進んでいる。
解体・再利用を考慮した設計を
また、権藤氏は建物の「解体・再利用」にも目を向けていくべきと指摘した。
現在の日本では、かつて大量供給したプレハブ住宅の多くが老朽化しており、修理などの必要が迫られている。しかし、型式認定を取得していたり、オリジナルの住宅部品を使用していることなどから、供給した住宅メーカーしか直せないという事例も少なくない。こうしたストックを今後どうしていくかが大きな問題になってくる。
一方で、解体・再利用をしやすい住宅供給を進める仕組みとして、欧州の取り組みは参考になる。欧州では建物を資源の貯蔵庫とみなす「Building as Material Banks」構想が進み、解体材を資源として管理・再利用する取り組みが活発化している。さらに、はじめから解体を考慮した設計である「リバーシブルデザイン」も主流になりつつある。
日本の住宅市場は、「住宅不足」から「住宅余剰」へと大きく変化した。今後は新築中心の住宅供給よりもストック活用の重要度がますます高まる。「建てて終わり」ではなく「持続的に再利用可能な資産」となるようなサイクルを住宅生産の仕組みに組み込むことが不可欠と言えよう。